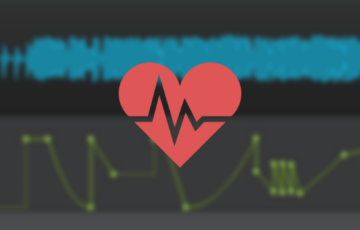曲がりなりにも10年DTMを続けていたら、ふとあることに気が付きました。
曲って作るのめっちゃ大変じゃないですか?
コード進行に時間がかかり、それに合うメロディに時間がかかり、歌詞に時間がかかって、ふと気が付けば締め切りです。アレンジとミックスはどこへ行ったのでしょう。
「作曲に慣れたらどんどん作業スピードが速くなるんやろなぁ…」これが10年続いています。
上手くなったのは時間がかかることを見越した余裕のありすぎるスケジューリングのみ。対症療法もいいところです。
いやむしろ10年がかりでようやく掴んだ違和感です。ここで活かさなければ次は何年後になるか分かったものではないので、なんとかならないか一度深く考えてみることにしました。
「何故、曲を作るのはこんなにも大変なのか?」
目次
「作曲ができない理由」を色々考えた結果
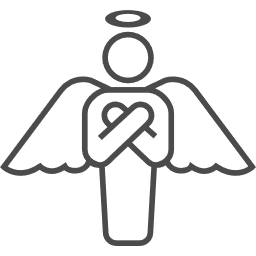
一度考え始めると、出るわ出るわ思い当たる節。
・コード進行やアレンジの引き出しが少ない
・作った曲の量が圧倒的に足りない
・作業工程に無駄が多い
・そもそも速く作ろうとしていない ……
好きで書いてるブログで落ち込む前に結論を急ぎます。
作業スピードが速くならない要素は上記のように無限に考えついてしまいました。
しかしその中で、一つ強めに「これは大きいかもしれない」と思ったものがあったのです。
「曲は無から生み出されなければならない」という価値観
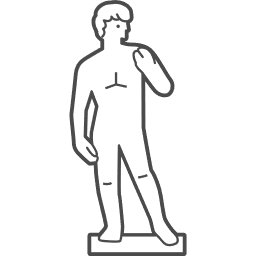
DTM、ひいては作編曲というものが、もうあからさまに”創造的な作業”なのは言うまでもありません。
世のミュージシャンは「アーティスト」と呼ばれ、ピアノやギターを髪を振り乱して弾き倒しながら、その卓越した感性をもって無から名曲を生み出している。そんなイメージが一般的です。
そういったアーティストやクリエイターに憧れて始めたDTM。その作業は、やはり独創的であれかしという姿勢に自然となってしまうものです。
要するに「一曲全てを”ゼロから生み出さなければいけない”と思い込んでいる」のが作業スピードを遅くしている原因なのではないかと思ったのです。
まぁこの文面ほど極端でなくとも、コード進行やアレンジを考える時に無意識下で「何も参考にせずに自分で考えた、オリジナリティのあるものにしたい」という感情が働いているために、完成までの時間がいたずらに増えてしまっているのだと考えられました。
それはある意味とても高潔な意識ではあると思いますが、現実に即して考えるといかんせん時間のかかりすぎるやり方です。
それを踏まえて考えた時、作業スピードを上げるためにできることは一つ。
「積極的に既存のモノを流用する」のです。
対処:「コード進行を流用する」

個人的に一番時間をかけてこだわってしまうのがコード進行です。
普段全く関わりのないようなコード同士が偶然隣り合い、見たことのないような表情を見せた時など、それこそ「尊い…😇」以外に言葉がありません。そういえばコードのカップリングって意外と見たことないですね。
しかしご存知の通り、この世のコード進行は全て出尽くしていると言われており、どれだけ時間をかけてオリジナリティ溢れる進行を作った(と思った)としても、それは既にどこかで使われている進行なのです。
「自分で見つけたオリジナルなコード進行」が幻想に過ぎないのならば、そこに時間をかける意味はありません。
こういった書籍やサイトから好きな既存曲のコードを拾い、流用することで時間を大幅に短縮できます。
曲の雰囲気を担うコードを借用するというのは大変勇気がいりますが、コードはその上にメロディやリズムが乗って初めて活きてくる要素なので、そこがオリジナルであれば元の曲とは全く別物に仕上げることが出来ます。既存曲同士でもコード進行が同じ、というケースは多いですしね。
イントロはあの曲の進行、サビはあの曲の進行…と、セクションごとに流用すると作りやすいですし、それを繰り返すことで「イントロは半音進行で下がっていく感じにしたい」といったイメージの具体化が容易になっていきます。
対処:「ループ素材を使う」
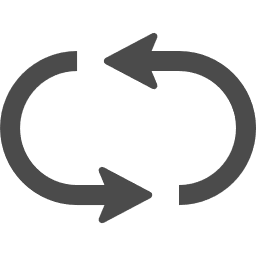
アレンジにおいては、作ったコード進行+メロに合わせてどんどん楽器を足していくというやり方が多いように思います。
その際に「何の楽器を足していいか分からない」「上手くハマるフレーズが出てこない」という場面で手が止まることが多いのですが、その突破口として適当にループ素材を当ててみるのが有効です。
ネット上には有料、無料問わず無数のループ素材が公開されています。音色(楽器、シンセなど)もほぼ何でもあるので、自分の曲の方向性をより強化できそうなループ素材をBPMだけ合わせ、片っ端から貼り付けて試聴することでインスピレーションを得ようというやり方です。
最近だとLoopcloudがそういうやり方に適した作りをしているソフトなのでオススメです。
アイディアが浮かんでしまえば自分で打ち込みなおしてもいいですし、気に入ったならそのままループ素材を採用してしまうのもアリです。(※素材の権利規約だけ気をつけてください)
しかし、Stylus RMXとかApple loopsみたいな有名どころのループ素材の場合は、そのまま使用するのは避けた方が無難です。少しDTMをかじっている人が聴けば一発でわかってしまうためです。flump○olのデビュー曲とか有名ですね。
露骨にそのままでなければいいという話なので、フィルターやピッチ変更など、ある程度加工してあげれば大丈夫です。
また、ドラムループは打ち込みの時間を大幅に短縮できるのでメリットがデカいです。
しかしループ素材ではフィルイン等で困ってしまうので、BFD3の内部パターンのような自分で打ち直せるループ(上の記事でも書いています)がオススメです。
対処:「プリセットを使う」
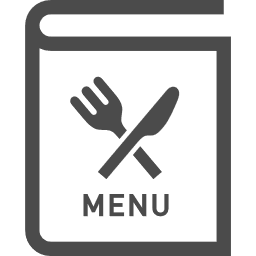
ミックス用のプラグインやシンセの音作りにおいて、気持ち的には「音を聴いて判断し、パラメーターを設定する」というやり方がカッコ良くて憧れがちなのですが、一度やってみてなんか上手くいかないな…と思ったなら、プリセットを使うのをお勧めします。
僕も長年、わけもわからず設定している癖に「プリセットはオリジナリティが出ない」と謎に意地を張って微妙な効果を生み出し続けてきたので、もうここで終わりにしましょう。
合いそうなプリセットを適用し、好みに合わせて必要な部分だけ弄る方が速い上にクオリティもある程度担保されます。
注意点としては、海外製のソフトの場合はプリセットも結構極端な設定になっていることがあるので調整が必要なことと、その調整の際にどのツマミが何を設定するのか?を簡単にでも理解しておく必要があることです。
ちなみにツマミを理解するコツは、音を出しながら最小値と最大値を行ったり来たりするようにグリグリ回すことです。そのツマミが及ぼす効果がわかりやすくなりますよ。

おわりに
半分以上自分に言い聞かせるような記事になってしまいましたが、それでも「独創的なやり方」に無意識に縛られているDTMerはきっと僕だけではないと思ったので、考えた事をまとめました。色んなご意見を頂けたら嬉しいです。
実際今まで曲を作ってきて、全てをゼロから考えた曲も、結果的にコードや要素を流用した形になった曲もありますが、どちらも同じように大切に思えていますし、世に出した時の人気も明らかにどちらかに偏るようなこともありませんでした。「気にし過ぎ」だったのかもしれませんね。
そしてここまで書いといて今更ですが、「ゼロから見つけた!考えついた!」という高揚感がエンジンになって一曲作れてしまったりなど、何も参考にせずに作ることにも別のメリットはあると考えています。今回の記事はあくまで、時間効率を上げるための視点に立って書かれたものです。
ただでさえ「とにかく質よりも量を出せ」と指南されがちな昨今です。一つの曲をゼロから生み出すというのは想像よりずっと手間暇がかかってしまうので、量を出すためにも肩の力を抜けるところは積極的に抜くことも大事なやり方だと思います。
「自分の中の高潔さ」をどれだけ排せるかが肝です。全てをゼロから生み出すのは、それこそいつでも挑戦できることなのですから。





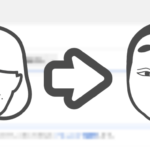



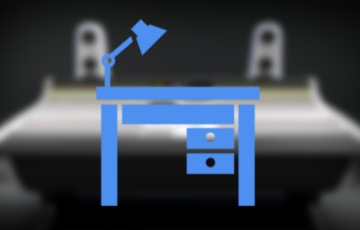
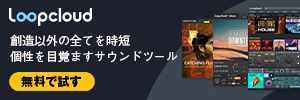
 「1176に火を入れる」は「
「1176に火を入れる」は「