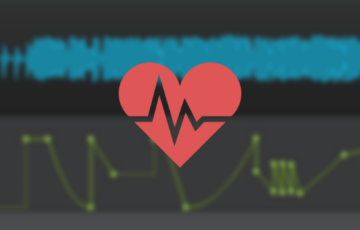DTMを始めた頃、イコライザー(EQ)と言えば「なんか音をシャリシャリさせたりモコモコさせたりできる謎のエフェクター」というフンワリした認識だったように思います。
包み隠さず言えば今もその認識のままフンワリ使っているような気もしますが、曲がりなりにも数年触っていると、
- 何ができるのか
- 何に使うのか
- 注意すべき事は何か
といった事が徐々に自分の中に形成されてきたりもします。
なのでこの記事では、特にDTMにおいてイコライザーが何故使われるのか?について、振り返りの意味も込めて解説してみたいと思います。
まだイコライザーにちょっと人見知りが出てるという方は是非、この機会に歩み寄ってみてはいかがでしょうか。
目次
イコライザーとは?
一言で言えば、「対象となる音の”音質を変えることができる”エフェクター」です。
まず前提として、この世に存在する全ての音は、低音から高音までの成分がどれだけの比率で含まれているか?で音質が決定しています。
例えばベースなんかは100人聴いたら120人が「低い音」だと感じると思いますが、実際には低音以外の音域(高音成分)もある程度含まれていたりします。

単に低音成分が多くて優勢なので、全体として聴くと「低い音」という印象の音質になっているに過ぎないのです。
あと余談ですが、その音成分の配合率は上の画像のように「周波数帯域」と呼ばれる波形型の区分で視覚的に表すことができます。
そしてイコライザーは、この周波数の任意の箇所を自由に上げ下げすることによって音質(=音の印象)を変えることができるわけです。何故上げ下げできるのかは全くもって謎です。
そうなると「何故、DTMにおいて音質を変える必要があるのか」という疑問が持ち上がってくるわけですが、それは上で出てきた「音には一番目立つ帯域以外の音成分も含まれている」という前提を踏まえると理解しやすくなります。
DTMにおける使用目的
EQは大抵、以下の2つの目的で使われます。
- 邪魔な帯域をカット(減衰)する
- 音作りの為にブースト(増幅)する
1.邪魔な帯域をカットする
曲の中では複数の楽器が同時に鳴るわけですが、そうなると一部、「他の音に遮られて聴こえにくい音」が出てきます。
DTMにおいて最もベタなのは「キックがベースと被って埋もれる」というケースでしょう。
どっちも低音楽器なので帯域が似通り、ぶつかった結果、鳴ってるのに聴こえない恵まれないキックが出来上がってしまう現象です。
こういう事例の解決策の一つとして、イコライザーで被っている帯域をカットして整理するという方法が取られます。
ベースとキックそれぞれの一番目立たせたい帯域を決め、それ以外の被っている不要な帯域をカットすることで両者の共存を図る、という寸法です。
例えば下の画像のように、130Hz辺りが目立っているベースがあるとします。

対して、キックは75Hz辺りが目立っているとしましょう。

目的とするミックスにも寄りますが、仮にキックがベースの下に来るようにしたい場合、ベースの75Hz付近より下をカットすることでキックの居場所を確保することができそうだ、とアタリを付けることができます。
逆にキックの130Hz付近もカットしてあげれば、もっとベースを聴きやすくもできそうですね。
こういったミックスにおける帯域の整理こそ、イコライザーに最も求められることが多い役割なのです。
2.音作りの為にブーストする
先ほどの帯域整理とは違い、今度は楽器単体、あるいはミックス全体の音の印象を変える為にイコライザーを使う場合の話です。
例えばハイハットの音がイメージより暗いと感じた場合、別の音色に差し替えるのも手ですが、イコライザーで高音域をブースト(増幅)することで明るい印象の音色に加工するという手段を取る事ができます。

イコライザーは周波数を下げるだけでなく上げることも可能なので、特定の周波数が持つキャラクターをより強調することができるのです。いわゆる「音作り」と呼ばれる処理がコレです。
逆に「シンバルが耳に刺さり倒して曲どころではない」みたいな時には高音域を下げる処理をすることになりますが、これも音作りと言えます。
増減は関係なく、音の印象を変える目的の処理は音作りである、という認識で問題ありません。
またこの音作りは楽器単体ではなく、ミックス全体に対して「最後の微調整」として適用される場合もあります。
トータルEQとも呼ばれる処理で、上記の音作りほど積極的な加工はせず、微妙な聴き心地の印象を整えるためにほんのちょっとだけ上げたり下げたりする事がほとんどです。
どちらかというとミックスよりマスタリング工程で仕上げとして用いられます。
グライコとパライコ
特に知らなくても困りませんが、イコライザーは2種類あることを覚えておくと友達にマウントを取れます。
イコライザーは基本的に、以下の2つのどちらかに分類することができます。アナログ、デジタルを問いません。
- グラフィックイコライザー
- パラメトリックイコライザー
グラフィックイコライザー(グライコ)
「イコライザーは任意の周波数を上げ下げできる」というのは上で書いた通りですが、グライコとはこの上げ下げできる周波数が決まっているタイプのイコライザーのことを指します。
初めて見た時は何の縛りプレイかと思いましたが、グライコの周波数は各帯域の重要な部分に焦点を当てて決定されている事が多く、悩まずに全体の音色を決定できる素早さがウリです。
特に初心者の場合は、グライコをイジり倒して各帯域の音色の特徴をザックリ把握するのをお勧めします。
「2kHzはシャリシャリ感を司る」みたいな帯域ごとの音の印象を一定の物差しとして自分の中に持っておくと、ミックスの際にバランスに問題のある帯域が肌感で測れるようになります。
パラメトリックイコライザー(パライコ)
グライコとは対照的に、増減する周波数を任意に指定できるイコライザーをパライコと呼びます。
1Hz以下の単位で詳細に周波数ポイントを設定できるため、より細かい処理がしたい場合はパライコを使用する事になるでしょう。
とにかく自由度が高い反面、「つい必要以上に加工してしまう」というダークサイドを常に併せ持つ諸刃の剣でもあります。
デジタルEQなんかはポイントを無限に追加できたりもするので、カットしすぎてほぼ無音みたいな事にならないよう注意が必要です。
使用する上での注意点
エフェクトは何でもそうですが、「掛け過ぎ」には注意を払うべきでしょう。
イコライザーで言えば、
やりすぎの例
- ブーストのし過ぎで聴き心地を損なう
- カットのし過ぎで迫力や音色の良さを失う
こういう例なんかが心配されます。
しかしこうやって文字で見ればすぐ分かりそうな違和感も、実際の作業ではなかなかどうして気が付きにくかったりするのです。
その原因はズバリ、比較対象が無いことにあります。
製作中の音源だけを聴き続けて作業しているとどうしても耳が慣れてしまい、違和感を覚えにくいという単純極まる要因です。
とはいえ原因がハッキリしている分、対策もしやすく、
- お手本となる曲と常に聴き比べながら処理をする
- 完成したミックスは1日~数日空けて、耳がフラットに戻った頃に聴き直す
といった行動で解決できます。作業に熱中した後は少しクールダウンの時間を設けるようにすると良い結果になりやすいです。
国数英社イコライザー
これほど「必要不可欠」という言葉が似合う例も珍しいですが、DTMとイコライザーはまさしく一心同体と呼べる間柄です。
考えてみれば曲というものは周波数の集まりであるわけで、ド直球に周波数をイジるイコライザーについて理解を深める事は、すなわち曲やミックスについて理解を深める事と同義なのです。
そこにEQと対を為すエフェクターであるコンプレッサーに関する知識が加わったなら、さらにミックスの質は担保されていくことでしょう。でも「完璧を目指す」とかはまたちょっと話が変わってくるので、今は見ないフリをしておくのがお勧めです。











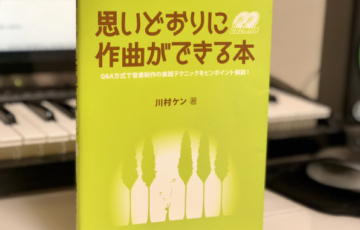



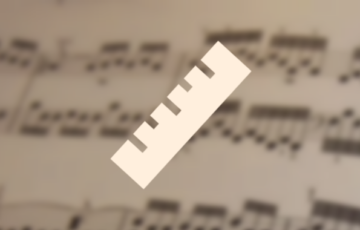

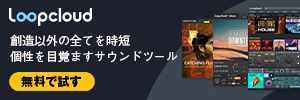
 「1176に火を入れる」は「
「1176に火を入れる」は「